◎4/14(月)休鍼(修行のため遠征)
△4/7(月)(入学式参列のため14:00より鍼療)
△4/12(土)9:00〜13:00鍼療(移動のため半日鍼療)
◎5/3(土)〜5/6(火)鍼診(雨が降らなければ竹林修行)
※夕方以降、勉強会、会議、研修などのため、不定期で17:00までに終了する日があります。ご不便おかけします。
さて、先週は大阪と高知に研修に行ってきました。
80歳の老中医(日本人ですが)と1日35人治療する僕と同級生の高知の名人にお会いしてきました。
本当に刺激でものすごく勉強になりました。
新たな出会い、昔からのご縁が紡ぐ学びと交流は本当に感動的です。
こちらの報告は、facebook、Instagramで報告します。
ぜひ、ご覧ください^^
春は五行では木に属する季節。
気が上りやすく、頭痛、めまい、耳鳴り、睡眠障害が起こりやすいきせ季節です。
そして、春といえば、花粉症です。
国民の約2人に1人が花粉症と言われており、まさには国民病とも言えるでしょう。
花粉症の症状は様々で、花粉に対するアレルギー反応によって引き起こされます。主な症状は以下の通りです。
・鼻の症状: くしゃみ、鼻水(透明でサラサラしたものが多い)、鼻づまり
・目の症状: 目のかゆみ、充血、涙目
・喉の症状: 喉のかゆみ、咳、違和感
・その他: 頭痛、倦怠感、集中力の低下、軽い発熱(まれに)
これらの症状は何かに似ていませんか???
そうです。
感染症の症状にそっくりなのです。
カゼを引くと免疫反応によって上記のような症状が起こりますよね。
花粉症も免疫反応による症状です。
これらの症状は、花粉の飛散量や個人の体質になどによって反応の仕方が変わります。
特に、春(スギやヒノキ)、秋(ブタクサやヨモギ)など、花粉の多い季節に現れやすくなります。
どこにでも存在する花粉に反応してしまうということは、免疫が過敏な状態だからです。
軽症の人は、春先のスギだけ、もしくはヒノキだけに反応します。
重症の人は、四季を通して、何かしらの花粉に反応するため、常に鼻炎に悩まされます(ここまで症状が悪化している人は、ハウスダスト、猫や犬のアレルギーもあります)。
さらに症状が進むと、免疫システムは自分自身の組織に反応して攻撃し始めます。
これが「自己免疫疾患」です。
僕の栄養学、機能性医学の師匠は「花粉症は自己免疫疾患の入口」と言います。
これは決して大げさではありません。
子供の頃、僕はアレルギー性鼻炎のため、粘膜が腫れてしまい、鼻呼吸がしにくく、耳鼻科の医師に言われるままに手術をしました。
当時はハウスダスト、花粉、動物など様々なものにアレルギーがありました。
最近は、病院に行かないのでわかりませんが、少なくとも鼻の症状で悩むことは全くなくなりました。
その最も基礎となることが食事です。
砂糖、小麦、乳製品、加工食品を一定期間(症状が落ち着くまで)、しっかり避けることです。
詳細は字数の関係で触れませんが、以上のものを摂っているかぎり、アレルギー症状と縁を切るのは非常に難しいです。
鍵となるのは、
・自律神経を整えること
・慢性炎症を処理すること
です。
慢性炎症は、
・咽頭(特に上咽頭、副鼻腔)
・口腔(歯茎、歯髄)
・腸粘膜
などにおいて起こります。
それから、病巣(上咽頭)の処理は「鼻みがき」がおすすめです。
しみますし、刺激的ですが、毎年薬を飲まなくてはつらい人が、薬を飲まなくて済むようになり、鼻がつまって眠れなかったのが眠れるようになるのはという話は日常茶飯事です。
「鼻みがき」をご希望の場合はお知らせください。

症状がつらい場合は、マスクや抗ヒスタミン薬で対策を取るのも有効ですが、いわゆる「抗アレルギー薬」は交感神経の働き強まります(交感神経優位)。
交感神経が優位な状態になると、腹部の内臓への血液の流れが低下します。
つまり、消化、吸収、解毒、生殖、回復修復などの働きが低下します。
栄養豊富なヘルシーなものを食べても身体に吸収されにくくなります。
自律神経を調整し、慢性炎症を処理して、栄養、睡眠、運動に取り組んで
4月も元気にお過ごしください!

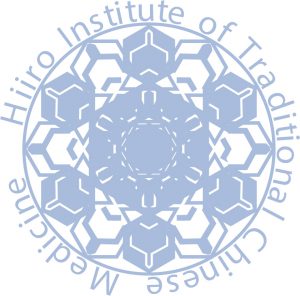
コメント